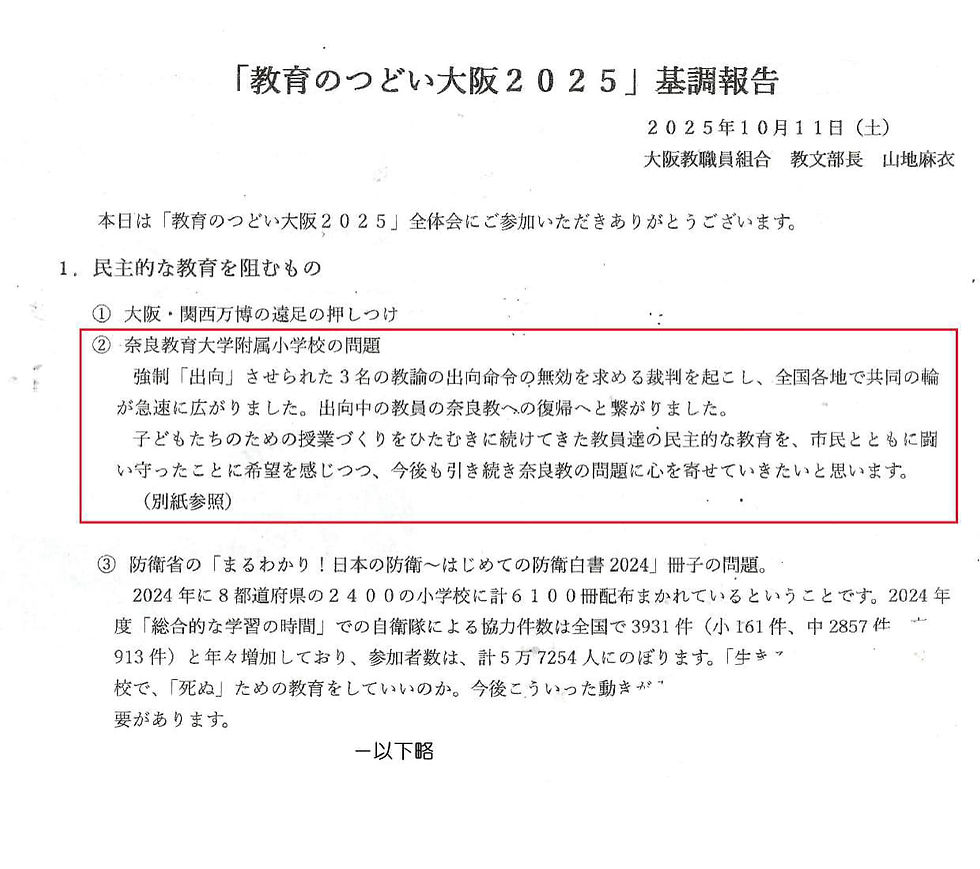『季刊教育法』に首藤先生の論文掲載(2025.1.21)
- まほろば

- 2025年1月21日
- 読了時間: 2分
『季刊教育法』No.223( エイデル研究所)に首藤隆介先生(名古屋造形大月教授)が「各学校の教育活動は誰が『評価』できるのかー奈良教育大学附属小学校への介入問題から考える-」を投稿しておられます。
以下に、要約して紹介させていただきます。
各学校の教育活動の評価(教育活動 改善のために、実施した教育活動にどのような価値があったのかを見定める行為)を行うのは、「各学校」であり、小学校学習指導要領解説総則編も、「全教職員の協力の下におこなれなければならない」(p.17)としている。
したがって、評価主体ではない奈良教育大が附属小の教育活動を評価し、改善の指示まで出すことは越権行為である。
大学による調査報告では、大学教員である調査委員が教科・領域ごとに調査を実施しているが、実践者以外の教育活動の評価は、表面的・部分的にならざるをえず、実質的・全面的な評価はできない。
指導要領自体が「大綱的基準」であり、ましてや「解説」や教科書会社の「指導書」は教育課程を拘束するものではない。
その内容にそっていないから「不適切」とし、満たさない項目のある教科の「回復措置」を命じるというのは、学校の裁量を理解していない、不当な命令である。
今回、「不適切」であったのは、附属小の教育課程ではなく、奈良教育大による評価内容及び評価行為の方である。
附属小が実践したきたことこそ、文科省が推奨する、いま学校が目指すべき教育課程編成である。