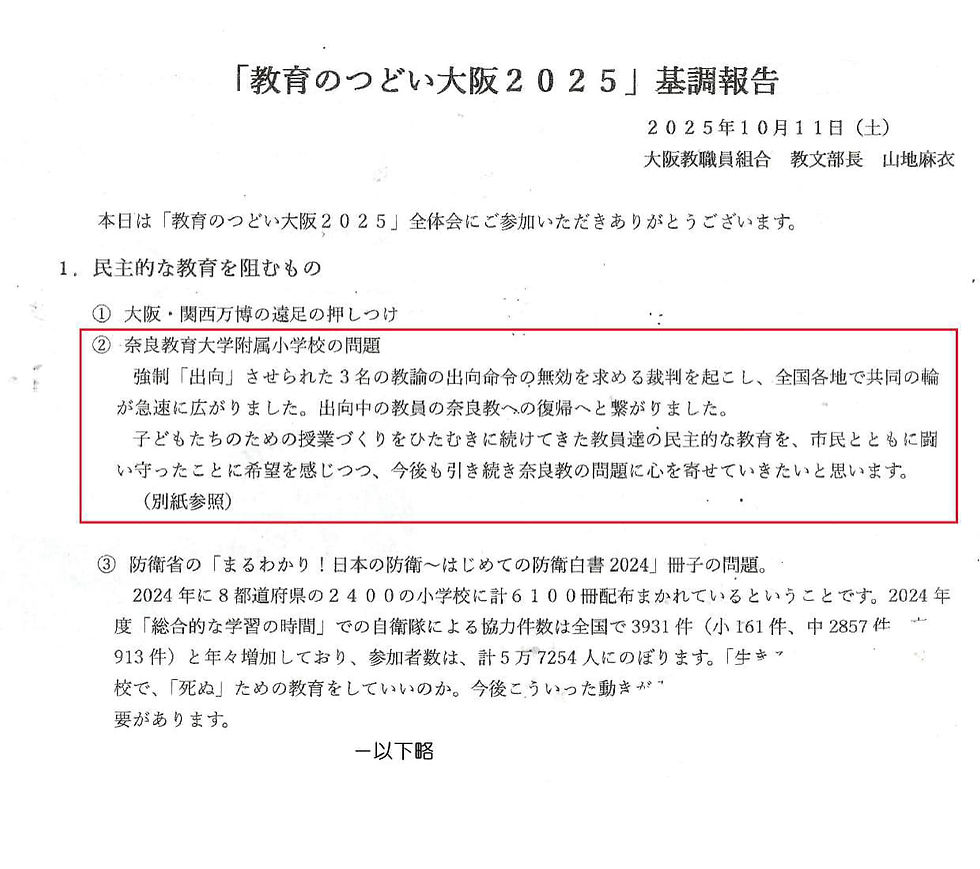近畿東海教育研究サークル合同研究集会で植田健男氏講演(2025.11.9)
- まほろば

- 2025年11月9日
- 読了時間: 4分
更新日:2025年11月12日

11月8日(土)、「2025年近畿東海教育研究サークル合同研究集会(奈良大会)」が行われ、全体会において植田健男さんの講演「次期学習指導要領の改訂と私たちの課題―『試金石』としての奈教付小事件―」が行われました。
全体では、100名を超える参加者がありましたが、奈良教育大附属小を守る会からは、現地参加36名、オンライン参加8名の計44名が参加されました。
植田講演は、次期学習指導要領の改訂に向けた議論の本質を問い直すとともに、奈良教育大学附属小学校事件を「試金石」として、教育課程の意味内容の変遷とその制度的背景を批判的に検討するものでした。
まず、「学習指導要領」という言葉の曖昧さに着目し、教育関係者でさえその本質を十分に理解していない現状が指摘されました。
学習指導要領は、現状、単なる「学習指導の要点」ではなくなり、文部科学省が定める教育課程の基準であり、教科書や入試、教員の指導にまで影響を及ぼす法的拘束力を持つ制度として扱われる、いわゆる「学習指導要領体制」が教育現場に強固に構築されています。
このような制度的枠組みの中で、「教育課程」の意味内容は大きく変容してきました。
戦後初期の1951年版『学習指導要領(一般編)』では、教育課程は「学校の指導のもとに、児童・生徒がもつところの教育的な諸経験や活動の全体を意味している」と定義され、「教育課程の構成は、本来、教師と児童・生徒によって作られる」とされていました。
これは、教育課程を学校の教育活動の全体計画として位置づけ、地域や保護者、専門家の協力のもとに編成されるべきものとする理念に基づいていました。
ところが、1958年改訂以降、学習指導要領は「官報告示」によって法的性格を強化され、学校現場では遵守が当然視されるようになりました。
すると、1958年改訂以降、教育課程は国が定める教育内容の集積とされ、学校の主体的編成権が大きく制限されました。
これに対して「教育課程の自主編成運動」が展開されましたが、実際には教育課程そのものの再定義には至らず、制度的従属が続いてきました。
しかし、近年の改訂論議においては、旧来の教育のあり方に対する反省から、「新しい時代に求められる資質・能力」重視の方向性が打ち出され、中央教育審議会の教育課程企画特別部会では「教育課程の再定位」が重要な論点となっています。
教育課程は、単なる教科内容の配列ではなく、学校の目的達成のために子どもの発達段階や地域の実情を踏まえて編成されるべき教育計画であると再定義されつつあるのです。
にもかかわらず、議論の中では「教育課程」と「カリキュラム」が混同され、「カリキュラム・マネジメント」という言葉が定義不明のまま使用されている点が問題視されています。
また、今日の「社会に開かれた教育課程」や「チーム学校」では、地域との連携が形式的に扱われがちであり、教育課程の本質的な意味が見失われています。
今回の奈良教育大学附属小学校事件では、県教委や文科省による教育課程への介入が顕在化しました。
教科書を主教材としない授業や、道徳の代替としての全校集会などが、「教育課程(=学習指導要領)の実施」に問題がある「不適切」「法令違反」な指導とされ、学習指導要領通りの指導の実施が強く求められ、教員の責任が追及されました。
この事件は、教育課程の編成権が学校にあるべきか、国にあるべきかという根本的な問いを再浮上させる契機となっています。
教育課程は本来、学校が地域や児童の実情に応じて編成すべきものであり、「教育課程の地域的共同所有」という視点が重要です。
その意味では、奈良教育大附属小は、その理念を実践してきたお手本のような学校だと言えます。
さらに、学習指導要領の「法的拘束力」についても再検討が必要です。
中教審答申では「大綱的基準として、法規としての性格」とされる一方で、現場では創意工夫の余地があるとされるなど、矛盾した説明が存在しています。
このような制度的曖昧さが、教育課程の編成と実施における混乱を招いているのです。
以上のように、植田講演は教育課程の意味内容の変遷を軸に、学習指導要領体制の制度的問題とその改訂に向けた課題を多角的に検討しました。
今後の改訂においては、教育課程の本来の意義を回復し、学校現場の主体性を尊重する制度設計が求められます。
許可を得て、植田講演のレジュメを公開します。ご活用ください。